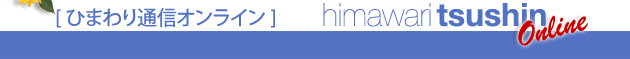ボクが医者を辞めた理由、
医者に戻った理由 (その1)
所長 毛利 一平
ひまわり診療所に来て2年が経ちました。古くからの患者さんたちにとっては、いつの間にか、どこからかふらっとやってきて、なんとなく居ついているように見えるかもしれません。長い長い時間をかけて、信頼関係を気づいてきた平野先生とは違って、「毛利には声をかけづらい」と感じておられる方が少なくないのではないでしょうか。
ひまわり通信でも、いきなりぽっと出てきて「新しい所長です」、なんて言われても「え、え、平野先生辞めちゃうの?」なんてびっくりしちゃいますよねぇ。
診察室で少しずつでもお話ができればよいのですが、「3分待って30分診療」なんて言っていた初めの頃とは違って、最近ではゆっくりと話をできないことも増えてきました。少しでも私のことを知っていただければと思い、しばらくこの場を借りて、私自身のことをお話ししようと思います。
私は一度医者を辞めています。もちろん医師免許を捨てたとかそういう話ではありません。医者になったきっかけや、学生時代に学んだことなどから、「病気を治す」ことよりも「みんなが健康ですごすことのできる社会づくり」に関心があったので、公衆衛生(病気の予防、特に職業病の研究)を専門とし、患者を診ない時期があったということです。
1988年、大学を卒業した私は、東京・立川の病院で2年間の臨床研修を受けることになります。すでに将来の専門を「公衆衛生」と決めていて、周囲からは「変なやつ」と思われていたと思います。「予防医学で医者の飢え死にを目指します」、なんてことも言っていましたが、将来的に患者を診なくなるとしても、まずは医者にならなくちゃと思いながら研修にいそしんでいました。
当時、臨床研修も2年目になると、本格的に外来診療を担当したり、夜間の救急を担当したりしていました。外来だと半日で30~40人を診なければなりませんし(本当に3分診療の世界です)、まったく寝る間もない夜間救急勤務などを経験しているうちに、もともと動機が不純だった(本気で臨床医になろうとは思っていなかった)私は、あっという間に燃え尽きてしまいました。
ちょうど、研修を終えて大学院へ進学するところだったからよかったようなものの、あのまま臨床の世界に進んでいたら、どうなっていたかわかりません。仮眠中に救急車のサイレンの幻聴が聞こえてきたり、本当に鳴っていたポケットベルの音を、夢だと思い込んで眠ってしまった時には、心底、ゆううつな気分になってしまいました。
外来で見ることが多かった高血圧や糖尿病も、救急の待合室にあふれていた喘息も、少なからず予防が可能な病気です。個々の患者と向き合って、薬を使って治療するよりも、そうした病気で苦しむ人がいなくなるような社会をどうすれば実現することができるか、そのことを研究したいと考え、臨床研修を終えた私は公衆衛生の大学院に進みました。
私が所属した教室が、公衆衛生とはいっても主に職業病を研究していたことで、私の進路も少しばかり思っていたのとは違ってしまいました。師事した教授の専門が職業がん(仕事で扱う化学物質などが原因で起こるがん)だったこともあり、自然と私も職業がんを研究のテーマとして選びました。六価クロム(発がん物質として有名。最近、小松川公園に埋められた残さいが問題になったばかりです)やコールタールによる肺がん、製鉄工場労働者の発がんリスクなど、毎日パソコンとにらめっこしながら、ああでもない、こうでもないと計算を繰り返す日々でした。
研究に没頭する日々は楽しくもありましたが、実際に職業病の患者を診ているわけでもないのに、「専門家」になってゆくのはおかしいとも感じていました。ただ、1960-70年代にはあちこちで少なからずあった病院の「職業病外来」も、私たちの頃にはだんだんとみられなくなり、私が専門とした職業がんも、大学院を終えるころには他に研究する者がほとんどおらず、私自身が絶滅危惧種となってしまっていました。
研究も思うようには進まず、正規の4年間で論文を仕上げられなかった私は、1年卒業を延期して、それでも書き上げることができず大学院を中退し、医学部で助手として働くことになります。何とも中途半端な状況ですが、すでに妻一人、子供一人だったこともあり、定職に就かねばなりません。こうして、研究と教育、そして少しばかり医者(週1.5日のアルバイトが可能でした)という生活が始まりました。1995年の2月、阪神大震災の直後でした。(つづく)