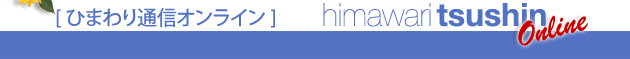ボクが医者を辞めた理由、
医者に戻った理由 (その2)
所長 毛利 一平
ボクが初めて研究者として職を得たのは、奈良県立医科大学の衛生学教室でした。当時はまだ、大学で働くのにどうしても博士号が必要というわけではなかったこともあって、大学院中退のまま雇ってもらうことができました。教授は森永ヒ素ミルク問題に取り組んだことで知られた先生で、教室にはボクのほかに3人の若手の助手(今では助教と言います)がいました。
一人は医学教育、一人は医療経済学、もう一人は公衆衛生、そしてボクは労働衛生を専門としていたわけです。みんな仲が良かったし、狭い世界ですがそれぞれ(ボクを除いて)「新進気鋭の」若手研究者と言われていたこともあって、「梁山泊みたいだね」なんて羨ましがってくれる人もいました。
しかし実際は指導してくれる先輩もなく、新しい研究テーマも見つけることができず、日々ぼーっとしているような状態でした。医学部などで「研究する」というと、ほとんどの人は、「白衣を着て、最先端の分析機械に囲まれて」というような印象を持たれると思いますが、そうではない世界もあります。「労働衛生の研究」となると、まず職業病の患者を見つけるとか、いろいろと調査をしたりするために企業や労働組合にしてもらわなければならないのですが、大学院を中退したなんとも中途半端な専門家の卵など、誰も相手にしてくれません。
学位論文も思うようには進みませんでした。大学院を中退した後も、教授の指導を受けることになってはいたのですが、いつも原稿の1ページ目から見直しが始まり、「てにをは」の修正が入り、毎回数行進んだだけで終わってしまうような状況が続いていました。今でこそ、その時の厳しい指導が役に立っていると思うこともないわけではないのですが、当時は本当につらくて、なんとなく指導を受けるのはやめてしまい、自分だけで何とかしようと思うようになりました。
電車に乗って東に向かう(所属していた大学院の方向です)だけで動悸がするような状態でした。
つらい経験でしたが、その時のことが今、診察室で、あるいは産業医として心の問題を抱える人に接するとき、とても役立っていることも確かです。
もう一度やり直すつもりで、アメリカの公衆衛生の大学院に留学しようと考えましたが、どうしても英語の資格試験で必要な点数に届かず、これも一旦あきらめることになりました。この長いトンネル、いったいどこまで続くのかと落胆していたところで、急に歯車がかみ合い始めたのですから、人生面白いものです。
暗い毎日に少し光が見えてきたのはちょっとしたきっかけからでした。奈良医大の玉石混交の助手たち5人ほどが集まって、毎週英会話を習っていたのですが、その集まりの中から「ネパールに調査に行こう!」という話が持ち上がります。長年ネパールで栄養調査などに取り組んでいる先生から、英会話仲間に協力の依頼があり、「じゃあボクも、ワタシも!」という感じで調査チームが出来上がりました。1996年のことです。
ボクの担当は首都カトマンズで三輪タクシー運転手の健康調査を行うことと、山岳地帯での栄養調査に同行していろいろと手伝うこと。その時の詳しい話はまたの機会としますが、その後も立て続けにベトナムでの工場調査に参加する機会を得るなどしたことで、ぼんやりと「労働衛生での国際協力」というテーマが見えてきました。日本ではだんだんと職場の環境も整ってきて、自分のような研究者はあまり必要とされていないのかなあ、と思っていましたが、広く世界に目を向ければまだまだ必要とされる場面はたくさんあると気づきました。
まずは小さなチャンスを生かして、こつこつと実績を積み上げよう、せっかくでき始めた研究者仲間とのつながりを大切にしようと、前向きになったところで大きなチャンス(!?)の到来です。
先輩研究者からJICA(当時は国際協力事業団)の専門家として、タイで働かないかと誘いを受けました。期間は2年間。ちょうど地に足を付けて頑張ろうと決心したばかりでした し、プライベートでもいろいろと難しい問題を抱えていたところだったので、少々悩みました。
アメリカ留学から一転してのタイ・バンコクへの赴任、妻は不満だったようです(南の国に対する妻のイメージは、「ヘビが多いから嫌い」でした)が、いろんなことを振り払うように飛び出しました。1998年3月のことでした。(続く)